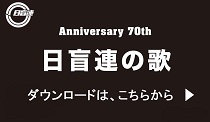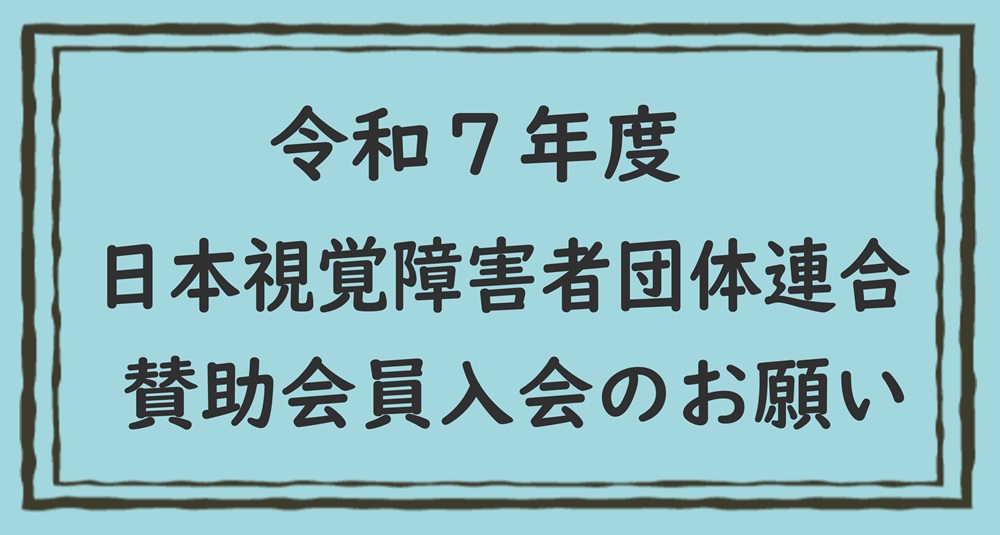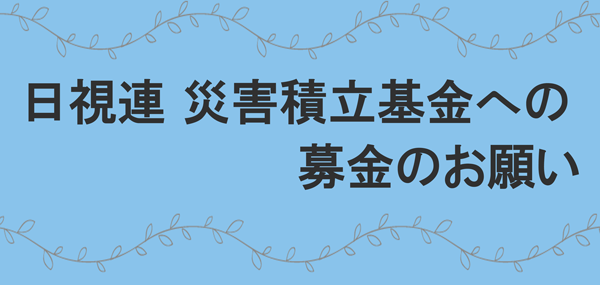第14回こども家庭審議会障害児支援部会 開催
令和7年9月29日、こども家庭庁の第14回こども家庭審議会障害児支援部会がベルサール飯田橋駅前においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合(以下、日視連)からは大胡田誠日視連将来ビジョン推進委員会委員長が構成員として出席した。今回は1.障害福祉計画及び障害児福祉計画(令和9~11年度)の見直し、2.障害児支援における人材育成に関する検討会について議論が行われた。
基本指針見直しのポイントとして障害児支援関係では、1.重層的な地域支援体制の構築及びインクルージョンの推進、2.重症心身障害児に対する支援、3.医療的ケア児等に対する支援、4.障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保、5.障害児支援における人材育成の推進、6.強度行動障害を有する障害児に対する支援の6項目が示された。また、障害児および障害者の共通項目として、1.地域における相談支援体制の充実強化、2.障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上、3.人口減少地域におけるサービスの維持・確保、4.障害福祉サービスの質の確保、5.きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備、6.障害者等に対する虐待の防止等、7.「地域共生社会」の実現に向けた取組、8.災害時における障害福祉サービス提供の確保、9.地域差の是正・指定の在り方等の9項目が示された。
これらに関して大胡田委員は次の意見を述べた。1.重層的な地域支援体制の構築及びインクルージョンの推進に関して、「保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等における障害児の受け入れ体制の整備状況を踏まえることが重要である」とあるが、ここに地域の学校や特別支援学校に通う児童も加えるべきと考える。2.障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保について、視覚障害児やその家族が相談にいっても適切に対応してもらえないことがある。視覚障害に関する専門性を有する相談員の研修が必要。また、この項目から外れるかもしれないが「伴走的な相談」に関連して言うと、通園・通学にかかる保護者の負担がとても大きいことから、是非その支援のための社会資源につなぐ相談を行ってもらいたい。
3.障害児支援における人材育成の推進に際しては、視覚障害児のための専門的・独自のノウハウ(点字、歩行訓練、PC操作のスキル等)の知識を含めた実践的なカリキュラムを盛り込んでもらいたい。4.人口減少地域におけるサービスの維持・確保に関連して、同行援護においては公共交通機関の利用が前提とされているが、人口減少地域では公共交通機関が乏しい現状にある。ヘルパーの自家用車等での移動をサービスとして認めてもらいたい。そうした形でサービスを維持できるよう図ってもらいたい。5.きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備のところで手話通訳者が上げられているが、視覚障害の関連でいうと、盲ろう者の通訳介助者、また点訳者、音訳者も明記してもらい、その養成を図ってもらいたい。