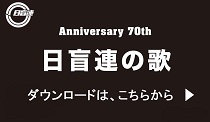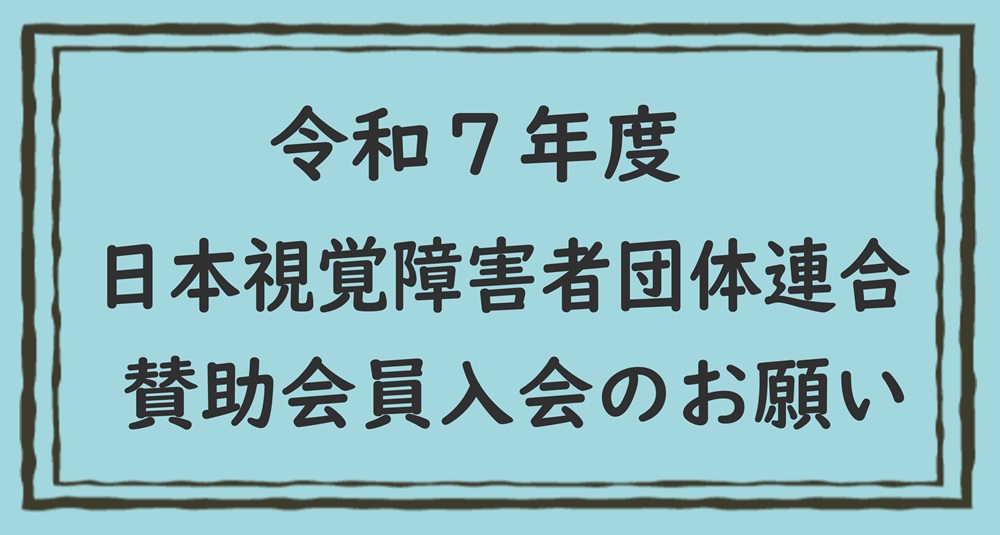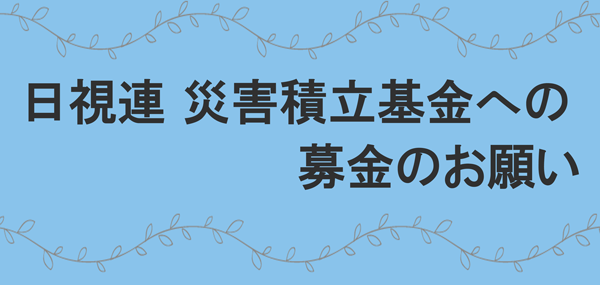全国視覚障害女性研修大会が新潟で開催
「第71回全国視覚障害女性研修大会(東海・北信越ブロック 新潟大会)」が、9月3日(水)・4日(木)の両日、新潟ユニゾンプラザ(新潟市)を主会場に女性協議会会員、関係者約300名が出席し開催されました。
3日午前の全国代表者会議では、常任委員に成田優子(岩手県)・宇都木泰代(神奈川県)・鈴木鈴子(岡山県)・清水幸枝(広島県)の4名が承認され、一部修正を加えて7つの議事すべてを採択しました。
午後の研修会第1部の講演では、講師に新潟医療福祉大学教育・学生支援機構中央教育センター教授の五十嵐紀子氏を迎え、「がんによって得た自由『自分を解放する力』」というテーマで展開しました。35歳で乳がんを告知されて一番辛かったのは「かわいそうに」という周りの目、正しい情報を得れば不必要に怖がることはない。様々な資源と出会えたことをキャンサーギフトととらえ、ガンになったあと結婚し、自分で決定し、自分に自由に生きていられると述べました。また、脳転移という再発を経てガン闘病から学んだことは、人に頼ることは弱さでなく技術であるということ。じっとしていたら人と出会わず、つながりも生まれない、自分を活かせる力は誰にでも備わっていると結びました。
第2部では、「視覚障害あるある あんな事こんな事、失敗談やそれを乗り越えたこと」をテーマとして、各ブロックから、6名の発表が行われました。若い頃は自分が視覚障害者であることを隠したり、白杖を持てなかったり、見えにくくなっていく中で葛藤しながらも自分でできることは何でもやりたいと試行錯誤したり、仕事と子育ての合間を縫って生きがいを見つけたり、変わるきっかけをつかんで考え方が変わったり、社会貢献している実体験を披露しました。表現力豊かに語られる女性ならではの体験に会場からは笑いと共感の拍手が絶えませんでした。
助言者の日視連吉松政春副会長は、自分も白杖を持って50年になるが地元では白杖をつけなかった体験など具体的に助言しました。最初は辛いこととして対応できないが、次第に自分なりの方法を見つけ出していくもの。小さなきっかけや挑戦、同じ悩み・苦しみ・失敗談を共有できる仲間作りが大切と述べました。
新潟県視覚障害者福祉協会の木村弘美理事長からは、失敗を笑いに変えるライフスタイルや全盲でよかったと言えるエネルギーはすごい、見えにくくなる中での工夫や努力は、見えにくくなって辛い思いをしている子どもたちに元気を与える内容であると述べました。また、周りの方々に支えられていることへの感謝が共通して印象的だったとご自身の経験も交えて述べました。
会場からは、簡単でおいしい唐揚げの作り方や食事介助の工夫などについて、長年の様々な経験による活発な情報提供、意見交換が行われました。
4日午前の式典では、主催者・歓迎の挨拶に続き、女性協議会顧問である石田昌宏参議院議員、花角英世新潟県知事、青柳正司新潟県議会議長、中原八一新潟市長からご祝辞をいただきました。
第2部の議事では、初日の全国代表者会議および研修会の報告、宣言・決議の採択を行いました。今年は、日々の買い物をはじめとする生活に関する項目、デジタル化や移動に関する項目、子育て支援や介護、災害・犯罪に対する視覚障害者のための具体的な方策など15項目が採択されました。
閉会式では、次年度開催団体である兵庫県視覚障害者福祉協会の大谷武会長より挨拶がありました。第72回全国視覚障害女性研修大会(近畿ブロック 兵庫大会)は令和8年9月3日(木)・4日(金)にANAクラウンプラザホテル神戸で開かれます。
採択された決議項目は次の通り。
1.食品の賞味期限、消費期限は視覚障害者にも見やすいように文字を大きくするよう要望する。
2.最低限の文化的生活を保障するために、物価上昇率に連動した障害基礎年金の増額を要望する。
3.地域生活での自立を高めるための歩行訓練を含む生活訓練、及び視覚障害を持つ親が安心して子育てができるよう、育児支援サービスに関する情報提供、利用支援、介助者の確保を要望する。
4.視覚障害女性が家族の介護を担う際に、適切な情報や支援が得られる体制の整備を要望する。
5.医療機関における情報保障(点訳、音声案内、触知案内等)の徹底と緊急時の入院や検査等の代筆代読を含め、医療従事者の視覚障害に対する理解促進を要望する。
6.視覚障害女性が選択できる職業の拡大と、個々の能力に応じた多様な働き方(リモートワーク、短時間勤務等)を可能にする環境整備を要望する。
7.視覚障害女性が行う家事の支援、及び外出支援、移動支援の更なる充実と、地域住民に対する理解促進を要望する。
8.災害発生時における避難情報、避難経路、避難所での生活情報が、視覚障害者にとってアクセスしやすい形で提供されるようにするため、防災計画に視覚障害者の意見が反映されるようにするとともに、避難訓練等に視覚障害者が参加しやすい工夫を凝らし、自助・共助の意識を高めるための啓発活動を要望する。
9.公共トイレはJIS規格に従った操作ボタンの形状、色並びに操作ボタン及びペーパーホルダーの配置とすること。さらに、点字や拡大文字による表示、トイレ個室や手洗い場までの音声案内や点字ブロックの敷設をするよう要望する。
10.飲食店、小売店等で進むサービスの無人化やセルフレジ化に対し、人的支援等の代替手段を設けることを制度化するよう要望する。
11.情報アクセシビリティの抜本的改善と多様な情報提供の推進を要望する。
12.鉄道駅において、視覚障害者が特急券や身体障害者割引を受けた乗車券等を円滑に購入するために、みどりの窓口等、有人の窓口や視覚障害者も利用できる話せる券売機を確保することを要望する。
13.全ての特急券が普通乗車券と同様の割引を受けられるよう要望する。
14.高速道路において、視覚障害者が同乗する車両がスマートインターチェンジを利用した際、障害者手帳の提示で割引きが受けられるようにすることを要望する。
15.防犯対策の観点から、無人駅にライブカメラの設置を強化し、指令センター内に係員を配置すること。また、事件・事故を未然に防ぐために、視覚障害者に積極的に声掛けすることを要望する。