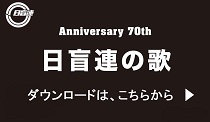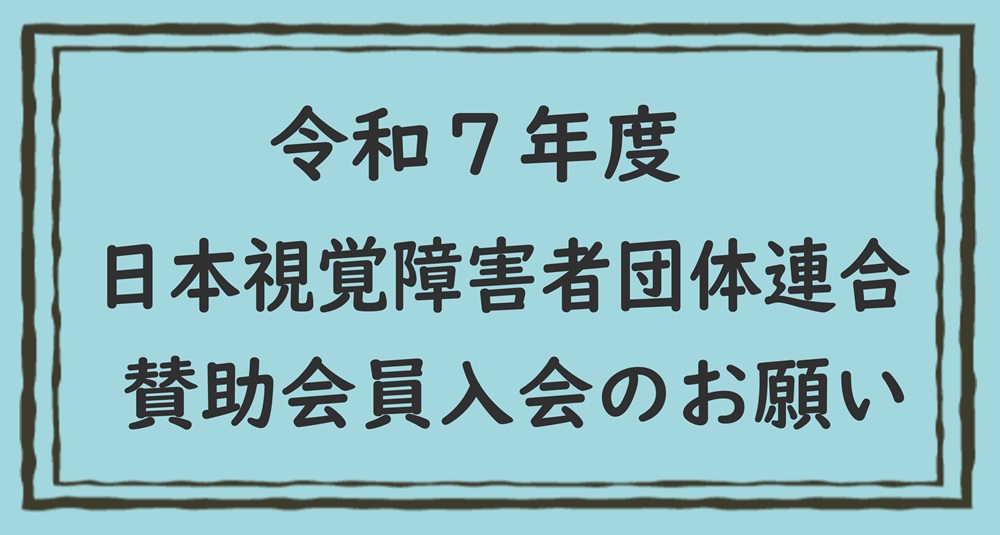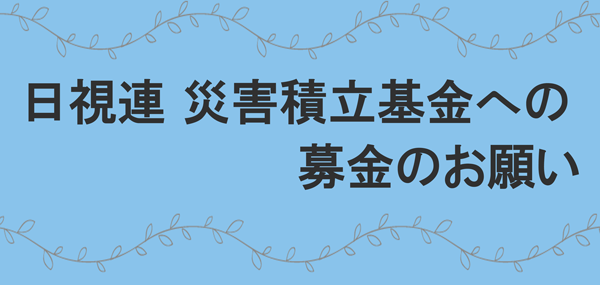第13回こども家庭審議会障害児支援部会 開催
令和7年7月29日、こども家庭庁の第13回こども家庭審議会障害児支援部会がベルサール御成門タワー3階においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合(以下、日視連)からは大胡田誠日視連将来ビジョン推進委員会委員長の代理として吉泉豊晴日視連情報部長が参考人として出席しました。
今回は1.障害福祉分野における地域差・指定の在り方、2.児者共通の障害福祉サービスにおける指定申請・届出事項の見直し、3.「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の検討状況について質疑が行われました。障害福祉分野における地域差については、障害福祉サービスデータベースから都道府県単位の数値が示され、地域差の実情が説明されました。また、都道府県等は障害福祉計画に定めるサービスの必要な量に達している場合に事業所等の指定をしないことができるが(いわゆる総量規制)、共同生活援助(グループホーム)は多くの都道府県において見込み量を超えた供給量となっていながら総量規制の対象となっておらず、障害者の支援ノウハウを十分持っていない民間事業者の参入につながったとして、サービスの質を保つためにもその取り扱いを検討する必要があること、事業者の指定について市町村が都道府県に意見を伝えることができる意見申出制度があまり行われていない実情に関して検討する必要があることなどが説明されました。
これに関連して吉泉参考人は、視覚障害児が対応困難との理由で放課後等デイサービスなどで受け入れてもらえない実状があることから、総量規制をやる場合に利用者数等の量的なものだけで解釈されてしまうと、視覚障害児の受皿になっている少数の事業所が影響されないか懸念されるとして、地域におけるニーズやサービスの専門性を勘案したものにすべきであると述べました。合わせて、都道府県内においても地域差があり細かく分析する必要があること、意見申出制度については市町村が量的なことだけでなく相談事業等を通じて把握したニーズを踏まえて意見を出してもらいたいことを述べました。
児者共通の障害福祉サービス(大人も子どもも利用する同行援護等がこれに該当する)における指定申請・届出事項の見直しというのは、指定申請の際に「利用する障害児の推計数」を届け出てもらうことにより、障害児を対象とする事業であることを自治体が把握できるようにするものであり、これを障害児対象居宅介護事業と位置づけて、障害児に対する性暴力防止策につなげることができるものと考えているとの説明がありました。これに関連して吉泉参考人は、障害児に対する性暴力防止策を講ずることは重要であり、そのための見直しに賛同すること、また、被害防止策を講ずることとなる事業者を公表することはサービス利用者が事業者を選択する際の材料となるので、広く周知するよう図ってもらいたいことを述べました。