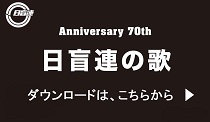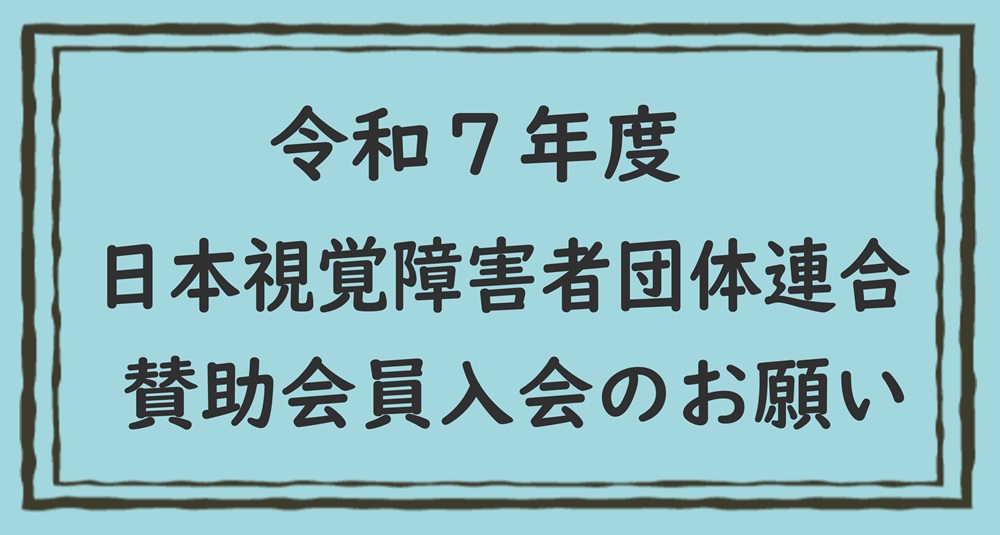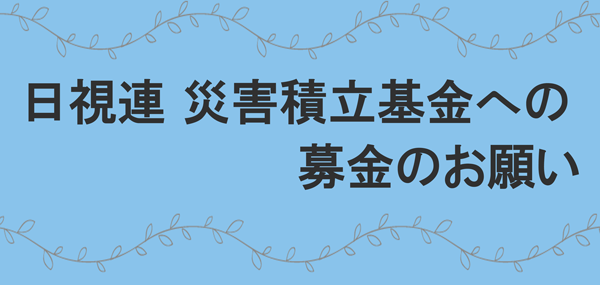厚労省の第148回障害者部会開かれる
令和7年7月24日、社会保障審議会障害者部会(第148回)がベルサール飯田橋駅前の住友不動産飯田橋駅前ビル1階においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合からは竹下義樹会長が構成員として出席した。
今回の議題は1.障害福祉分野における地域差・指定の在り方、2.「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」の検討状況の二つだったが、それぞれ事務局の説明のあと質疑が行われた。障害福祉分野における地域差については、障害福祉サービスデータベースから都道府県単位の数値が示された。生活介護、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援(A型、B型)それぞれについて都道府県別18歳以上人口に占める利用者数割合や利用者の伸び率が示され、地域差の実情が説明された。また、都道府県等は障害福祉計画に定めるサービスの必要な量に達している場合に事業所等の指定をしないことができるとの説明があった(いわゆる総量規制)。これは地域差の縮小につながるとともに、昨今、障害者のケア・サポートのノウハウを十分持っていない民間事業者が参入して問題になることがあるが、そうした状況に歯止めをかけてサービスの質を保つ意味合いがあるとのこと。総量規制について竹下会長は、サービスの質を保つ側面はあるかもしれないが、規制したからと言って質が保たれるわけではないとし、量的な面と質的な面(利用者の支援の実情)を一体的にとらえる必要があると指摘した。そのうえで、総数だけをみて総量規制するのでなく障害種別の状況等を細かく分析して行うべきと発言した。たとえば、視覚障害者にしっかりと対応できるグループホームを望む声が多く寄せられるが、そうしたホームは実際には少ない。視覚障害者を受け入れられないとするグループホームが少なくない。規制の際はそうした実情を踏まえたものにしてもらいたいと述べた。また、通所型の施設や日中活動の場は、身近な地域にそうした社会資源があるかどうかが大事になると指摘し、都道府県単位でみるだけでは不十分であり、市町村単位や地域圏といった細かい視点でみる必要があるのではないかと述べた。
2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関しては、竹下会長が質問と意見を述べた。中山間・人口減少地域等で福祉サービスを効果的に行うため、介護保険と障害福祉の分野を超えて福祉サービス共通課題に対応するというのは良い方向性だと思うが、その場合、65歳問題をどうするかが課題となる。65歳になると、障害福祉から介護保険への移行が原則とされているが、それが障害者に不利に働くとして裁判の訴訟事案になっている。この問題を解決しないと分野を超えた調整は難しいとして、どう考えるかを質問した。
また、介護と障害福祉を一体的に行う場合、それに医療・保険も組み入れて取り組む必要があるとの意見を述べた。65歳問題の質問に関して事務局からは、介護保険の部会と障害福祉の部会それぞれで議論してもらい調整する必要があるが、厚生労働省としては一人一人のニーズに応じた支援が行われるよう方針を示しているところであり、裁判の行方にかかわらずその方針を今後も進めたいと回答した。