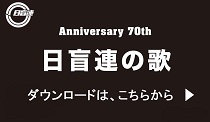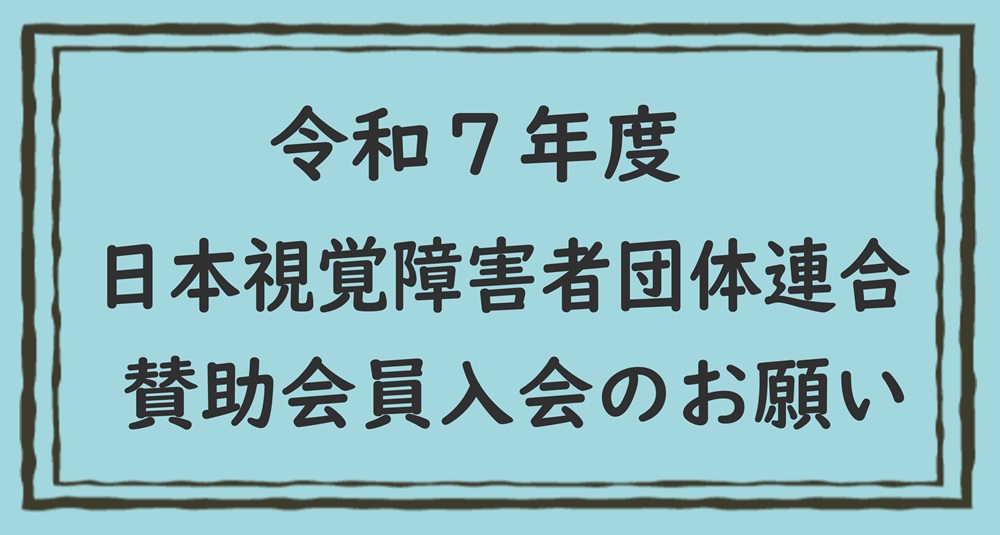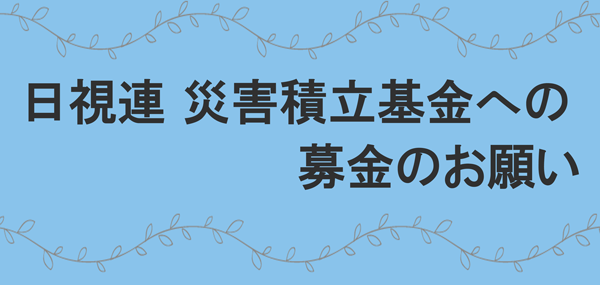第84回障害者政策委員会開かれる
令和7年7月16日、内閣府の「第84回障害者政策委員会」が中央合同庁舎第7号館13階共用第1特別会議室をホスト会場として、オンラインを交えたハイブリッド方式で開催され、日本視覚障害者団体連合からは田中伸明副会長が構成員として出席しました。
今回は、1.つなぐ窓口(相談窓口)、2.手話施策推進法の施行、3.「ともともフェスタ2025~迎賓館からはじまる共生社会~」開催のそれぞれについて報告があり、質疑が行われました。
つなぐ窓口(障害を理由とする差別の解消に向けた相談窓口)は、試行実施期間(令和5年10月から令和7年3月)を経て、今年4月から本格実施されています。相談の連絡先電話は0120-262-701(10時から17時)です。試行期間における相談件数が4602件で、相談者としては障害者(その家族や支援者を含む)が8割、事業者が1割、そのほか自治体等が1割という構成でした。相談者の障害種別では精神障害が全体の約4分の1、視覚障害は314件(6.8%)、盲ろうが3件(0.1%)でした。
手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)は、手話の習得支援(手話が必要なこどもや保護者等)のほか、学校教育や大学、職場、地域生活(災害時を含む)、文化芸術活動・スポーツ・レクリエーションの各分野における手話の普及、並びに国民の理解と関心の増進、人材の確保、調査研究の推進等を定めた理念等です。公布日施行は令和7年6月25日です。事務局が概要を説明したあと、全日本ろうあ連盟の石橋大吾理事長が法律制定までの経緯や今後の具体化促進の必要性について述べました。
「ともともフェスタ2025~迎賓館からはじまる共生社会~」は、今年5月30日・31日に迎賓館赤坂離宮で開催されたイベントで、2千人以上の参加者がありました。内容としては、冒頭で石破茂総理及び三原じゅん子内閣府特命担当大臣の挨拶があり、ステージパフォーマンスでは舞はんど舞らいふによる手話ダンス、日本盲導犬協会による理解促進ステージ、ミュージック・シェリングによるインクルーシブ演奏が行われました。出展ブースでは各種障害者団体・教育機関・企業等が出展しました。キッチンカーによる飲食の販売もありました。また、バリアフリーの取組例として、手話や要約筆記による情報保障、バリアフリートイレ、バリアフリーマップなどの紹介が行われました。
田中副会長は、「ともともフェスタ2025」が短い準備期間ながら充実した内容であったこと、イベントの広報動画が950万回再生され関心を寄せる人が多かったことを踏まえて、2026年度以降の開催を望むとの趣旨を込めて評価しました。また、手話施策推進法では手話が日常生活・社会生活でなくてはならないものと位置づけられており、手話が使われるようにするための環境を整備することと、その際に障害当事者の意見を踏まえることが重要であると述べました。加えて、現在、民事裁判において手話通訳者の配置に係る費用は訴訟費用と位置づけられていて配置者が負担することとされているが、そのことが、手話が意思決定に欠かせない手段であるとしている手話施策推進法と整合性がとれるかどうか、改めて検討する時期にきていると指摘しました。