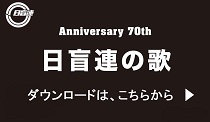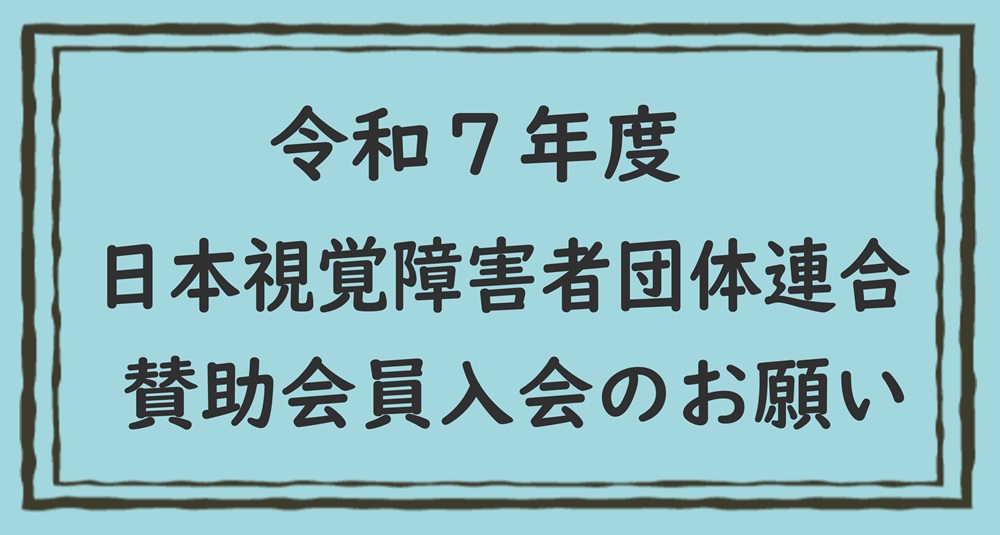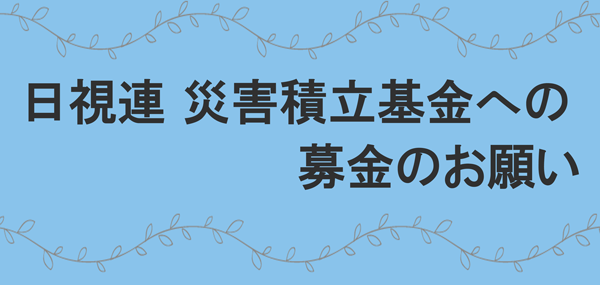第12回こども家庭審議会障害児支援部会
令和7年7月4日、こども家庭庁の第12回こども家庭審議会障害児支援部会がベルサール御成門タワー3階においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合からは大胡田誠日本視覚障害者団体連合将来ビジョン推進委員会委員長が構成員として出席しました。今回は、まず部会長・部会長代理の選任が行われました。部会長には有村大士日本社会事業大学社会福祉学部教授が互選により選任され、部会長が小野善郎おのクリニック院長を部会長代理に指名しました。
議題としては、1.第2期障害児福祉計画の成果目標の実績及び第3期障害児福祉計画の成果目標、2.障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等の見直し、3.今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会、4.療育手帳の在り方の検討状況、5.「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の検討状況について事務局の説明があり、質疑が行われました。今後の障害児福祉計画(第4期)の目標設定に関しては、まずは障害児部会等の意見を踏まえて国が基本指針を設定し、その指針に即して市町村と都道府県が障害児福祉計画を作成するというプロセスになることが説明されました。これに関して大胡田構成員は、第3期計画の実績が示されないと基本指針について議論できないと指摘し、実績がどうなっているかを質問しました。これに対して事務局からは、第3期計画の期間が令和6年度から8年度までで最終的な実績を示すことはできないが、議論の手掛かりとして途中経過における実績を提示するよう検討したいとの回答がありました。ちなみに、第4期計画の期間は令和9年度から11年度だが、今から準備段階として議論を進める予定です。
また、大胡田構成員は、障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等の見直しに関連して、支援を必要とする障害児が確実に支援を受けられるような給付の在り方・枠組みにしてもらいたいと述べました。自治体によっては放課後等デイサービスを無償化しているところがあります。そのこと自体が必ずしも悪いわけではないが、サービスの定員枠が埋まってしまって、切実に支援を必要とする障害児がサービスを受けられないという実態が生じてしまいます。そうした状況にならないような給付の在り方にしてもらいたいと発言の趣旨を説明しました。そのほか、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会は、団塊の世代の子どもたちが65歳になる2040年に人口減少、介護人材確保、地域包括ケアとの体制確保の問題が更に顕著になることを踏まえて対応策を検討するものではありますが、これまで主に高齢者を対象に検討されてきた経緯があります。大胡田構成員は障害者団体の関係者がこの検討会の委員に一人もいないことを指摘し、是非委員に加えてもらいたいこと、それが難しいのであれば障害者団体にヒアリングを行って意見を反映させてもらいたいことを要望しました。