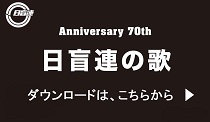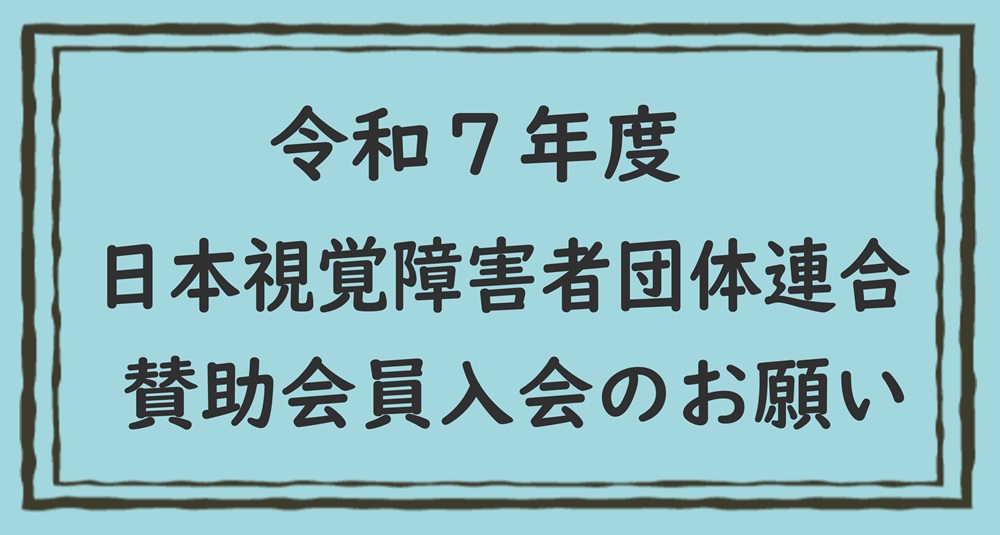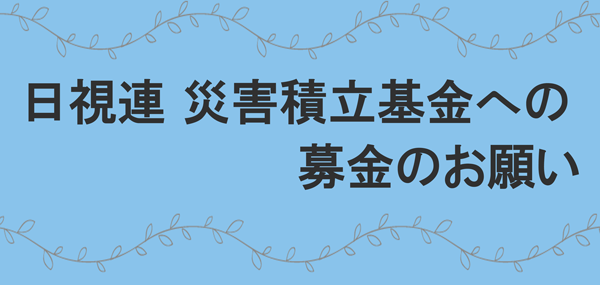厚労省の第147回障害者部会開かれる
令和7年6月26日、社会保障審議会障害者部会(第147回)がベルサール六本木(地下1階ホール)においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合からは竹下義樹会長が構成員として出席しました。
今回の議題は、1.第6期障害福祉計画の成果目標の実績及び第7期障害福祉計画の成果目標、2.療育手帳の在り方の検討状況の二つだったが、その他に報告事項として3.「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の検討状況、4.成年後見制度の見直し等、5.障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会、6.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第2期)についてそれぞれ説明がありました。
竹下会長は、今後の障害福祉計画に係る基本指針の策定のところで、「共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方」と書かれていることに関連して、総量規制を問題視した。総量規制を大枠で適用した場合、たとえば、総量規制があることを理由にしてグループホームで「視覚障害者は受け入れられない」と言われることにつながる危険があるとして、その適用は慎重に行うべきであると述べました。
療育手帳(知的障害者の手帳)については法的な位置づけはなく、自治体ごとに判定方法や認定基準にばらつきがあります。そこで、(1)国際的な知的障害の定義や自治体の判定業務の負荷等を踏まえた判定方法や認定基準の在り方、(2)比較的軽度な知的障害児者への支援施策の在り方、(3)統一化による関連諸施策への影響、(4)法令上の対応等について引き続き検討するとの説明がありました。
これに関連して竹下会長は、視覚や聴覚に障害のある知的障害者への対応では判定や支援の在り方に工夫が必要であり、そうした重複障害も視野に入れた対応策を検討すべきであると述べた。また、国際的な障害の定義に照らすと、日本の視覚障害や聴覚障害の定義の範囲が狭い。身体障害の定義についても国際的な定義を参照して見直してもらいたいと発言しました。
「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会は、団塊の世代の子どもたちが65歳になる2040年に人口減少、介護人材確保、地域包括ケアとの体制確保の問題が更に顕著になることを踏まえて対応策を検討するものだが、主に高齢者を対象に検討されてきたところ、障害者・障害児福祉も含めて検討し、必要な事項については障害者部会に諮るとの説明がありました。
施設から地域への移行を図るための「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」については、コミュニケーションに障害のある聴覚障害者や視覚障害者の当事者団体が検討会の委員に加わっていないことへの不満の声が上げられました。