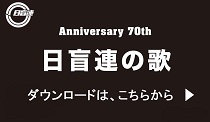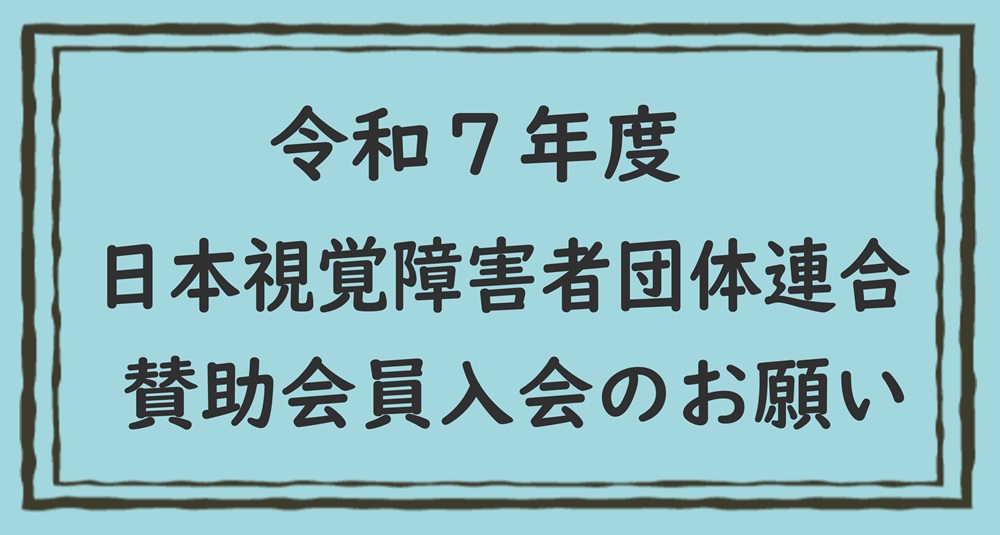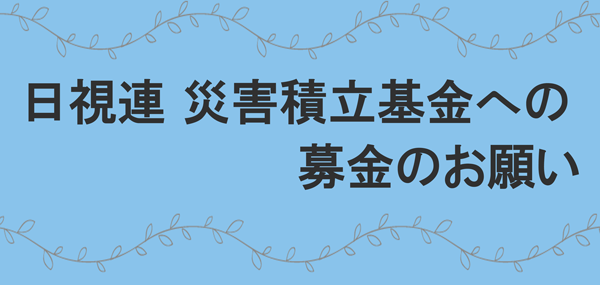障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会
令和7年6月25日、厚生労働省の「第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」が厚生労働省18階専用22~24会議室をホスト会場としてオンライン参加を交えて開催され、日本視覚障害者団体連合からは田中伸明副会長が構成員として出席しました。
今回は、就労継続A型事業所(以下、A型事業所)の障害者雇用率制度における取り扱いについて議論が行われました。A型事業所は、直ちに一般就労に就くことが難しい(あるいは希望しない)障害者の受け皿としての福祉的就労の場であるが、一方、最低賃金法や雇用保険法等の労働法が適用される形で雇用契約に基づいて障害者を雇っています。そのため、そこで働く障害者は障害者雇用率にカウントされ、法定雇用率を超える場合は障害者雇用納付金に基づく調整金・報奨金(以下、報奨金等)がA型事業所に支給されています。事務局からそうした説明があり、質疑が行われました。
なお、令和6年度の障害者の解雇者数は約9300人で、そのうちA型事業所の解雇者数が約7300人(おおよそ8割)を占めました。このA型事業所を解雇された障害者のうち、再就職決定者は約2200人、就労継続支援B型事業所等への移行者(予定を含む)は約3800人となっています。この背景にはA型事業所の減少傾向、並びに運営の厳しさがあると推測される旨の説明がありました。これに関して、福祉施策の補助金を受けるA型事業所が雇用率制度の対象になること、および報奨金等の支給対象になることについて疑問・違和感があるとの意見がありました。
その一方、労働法が適用されていること、および最低賃金の引き上げや物価高あるいはA型事業所で障害者の支援に当たる職員の賃金が低い水準にあり、報奨金等の対象外になると事業運営が更に厳しくなることなどの理由で、雇用率へのカウントと報奨金等の支給を引き続き行うのが適当との意見もありました。また、雇用率のカウントと報奨金等の支給を切り分けて、それぞれ見直すか否かを判断すべきとの意見も出されました。
田中副会長は、A型事業所が一般就労に向けて訓練する場であると同時に、必ずしも一般就労に移行することを希望しない人の働く場という側面もあり、多様な就労機会を提供する重要な役割を担っていると指摘しました。また、A型事業所は働く障害者への合理的配慮についてノウハウを持っており、企業等へのそのノウハウの発信が障害者の一般就労への移行を進める手掛かりになるが、そのためには事業所内で障害者を支援する職員の待遇がしっかりしたものでなければならず、その観点から報奨金等の支給を引き続き行った方が良いのではないかと発言しました。A型事業所には合理的配慮について積極的に発信し、合理的配慮の基盤づくりに貢献してもらいたいと述べました。この合理的配慮の提供に関しては他の委員からも同様の趣旨の指摘がありました。
そのほか、障害者雇用促進法が一般就労を促すことを目的としていることから、一般就労への移行の取り組み・実績を勘案して判断すべきとの意見、特例子会社や事業協同組合等算定特例(複数の中小企業が障害者雇用に取り組む方式)との関連も考慮する必要があるとの意見など様々な発言がありました。
最後に事務局および座長は、雇用関係の法制度と福祉関係の法制度の兼ね合いを整理し、実態を踏まえながらも制度としての整合性を保つ必要があり、更に検討を進めたいと述べました。