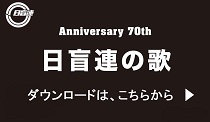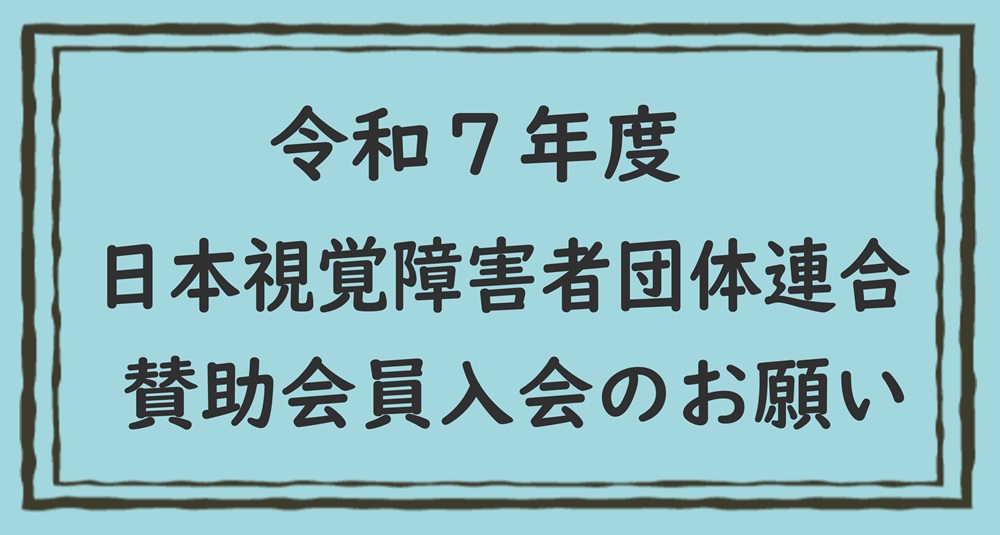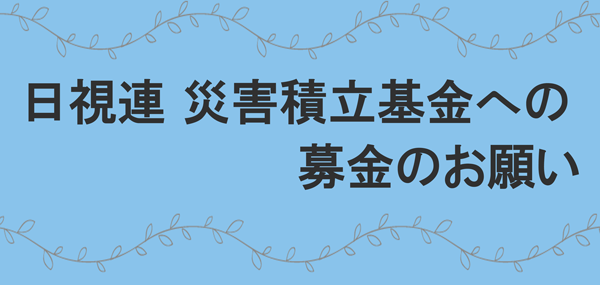障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(2)
令和7年4月14日、厚生労働省の「第4回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」が中央合同庁舎5号館3階共用第6会議室をホスト会場としてオンライン参加を交えて開催され、日本視覚障害者団体連合からは田中伸明評議員が構成員として出席しました。
今回の議題はヒアリング等を踏まえた意見交換でしたが、資料としては「関係者ヒアリングにおいて出された意見と今後の進め方について」および「諸外国の障害者雇用促進制度について(中間報告)」が配布されました。研究会で議論するテーマには障害者雇用の質、障害者雇用率制度等の在り方の二つがありますが、後者の論点には
1.障害者手帳を所持しない難病患者等の取り扱い、
2.就労継続支援A型事業所やその利用者の位置づけ、
3.精神障害者の重度区分の設定、
4.常用労働者数が100人以下の事業主への障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲の拡大
があります。
配布資料には、これらテーマについて関係者にヒアリングを行った結果が取りまとめられています。また、諸外国の障害者雇用促進制度についてはドイツ、フランス、アメリカ、イギリスの4カ国の状況および日本との比較が紹介されました。なお、障害者雇用率制度はドイツとフランスにはあるが、アメリカとイギリスにはありません。田中委員は次の趣旨を発言しました。
(1)雇用の質をみるための客観的指標が必要であり、公的部門で作成されている障害者活躍推進計画が参考になるが、それをそのまま用いるのではなく、障害者側の観点から職場における情報保証、キャリア形成のための研修の受講、昇進・昇格といった項目を含めて指標を整理する必要があります。
(2)障害者手帳を所持しない人については、働く上での困難度を勘案しながら、雇用率制度とは別の枠組みで支援する仕組みを検討するのが良いのではないか。
(3)就労継続支援A型事業所の位置づけについては、労働法が適用されていることから雇用率制度の対象外とすることは適当でないと思いますが、福祉施策の支援も受けていることを考慮すると、民間企業で障害者雇用を一層促進するための事業協同組合算定特例に関して、その対象からA型事業所を外すのが適当と考えます。
(4)労働者100人以下の事業所から納付金を徴収することについては、障害者雇用への意識を喚起する観点から徴収するのが良いと考えます。その際、規模が小さいが故の難しさがあることを考えて、障害者雇用の環境整備にかかわる支援を合わせて行うようにしてはどうでしょうか。