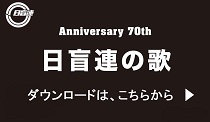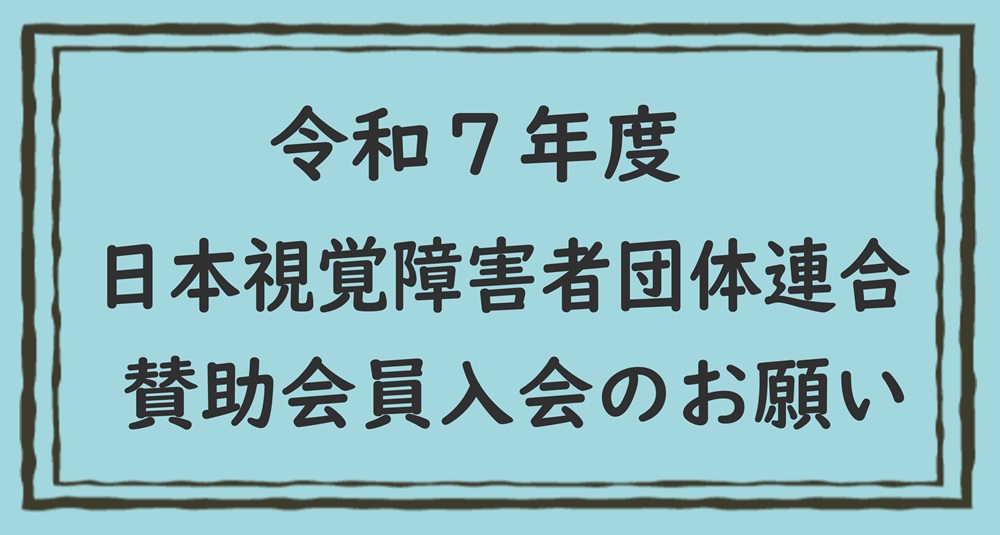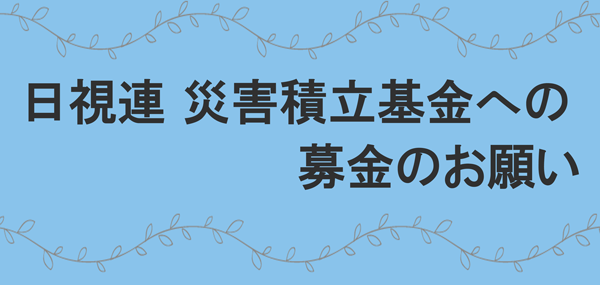厚労省の第146回障害者部会開かれる
令和7年3月14日、社会保障審議会障害者部会(第146回)がベルサール飯田橋駅前においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合からは竹下義樹会長の代理で吉泉豊晴情報部長が参考人として出席しました。
今回の主な議題は、障害福祉計画及び障害児福祉計画並びに外国人介護人材の訪問系サービスへの従事であり、それぞれ事務局による説明の後に質疑が行われました。障害福祉計画及び障害児福祉計画は、国が示す基本指針に即して市町村・都道府県が作成するもので、第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9年度~11年度)に向けて、まずは共通認識を持ち、本格的な検討の準備に入るものであるとの説明があり、計画の目標設定について主に次の検討事項が示されました。
(1)地域の実情に即した実効性のある計画の策定(障害福祉サービスデータベースの活用等)
(2)障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策
(3)都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村が意見を申し出る仕組みの推進
(4)共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行の状況も踏まえた事業所指定の在り方
(5)利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取り組み。
吉泉参考人は、基本指針に「障害者の権利の重視」を明確に提示すべきであること、障害福祉サービスの地域差の是正を是非進めてもらいたいことを述べました。
障害者の権利の重視に関しては、たとえば、同行援護の利用資格があるにもかかわらず、病院にいく際に通院等援助(院内でのサポートはヘルパーではなく病院スタッフに任される)を使うよう自治体から言われ、病院内での円滑な移動や書類の読み書きに支障をきたす事例があることから、同行援護の利用を権利として明確に位置づける必要があることを述べ、他にも障害者の権利という考え方が希薄であることから生ずる問題があることを指摘しました。
地域差の是正については、視覚障害者に対応できるサービスの担い手が特に都市部以外で不足している実態を踏まえ、従事者の報酬の在り方を含めて人材の確保とその事業所への所属の促進に取り組んでもらいたいと発言しました。
外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、EPA(経済連携協定)に基づく在留者及び留学生であって介護福祉士の資格を取得したものは、既に訪問介護等の業務において介護人材として働くことが認められているが、技能実習生及び特定技能(人手不足対応のため一定の専門性・技能を有する外国人を受入れるもの)については認められていない。これを介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での1年以上の実務経験等がある場合に認めるというのが今回の改定であるとの説明がありました。訪問介護等の業務には同行援護や家事援助等の居宅介護も含まれる。これに関連して吉泉参考人は、見えるものを指で指し示しながらコミュニケーションをとるといったことが難しい視覚障害者の場合、言語によるやりとりが重要になることから意思疎通が適切に行えるか不安があるとした上で、実際の訪問系の業務に従事する際の見習い実習等を通じて留意点を整理し、それを外国人の介護人材と障害者の双方に伝えることが必要であると述べました。