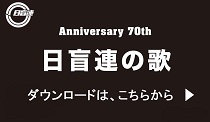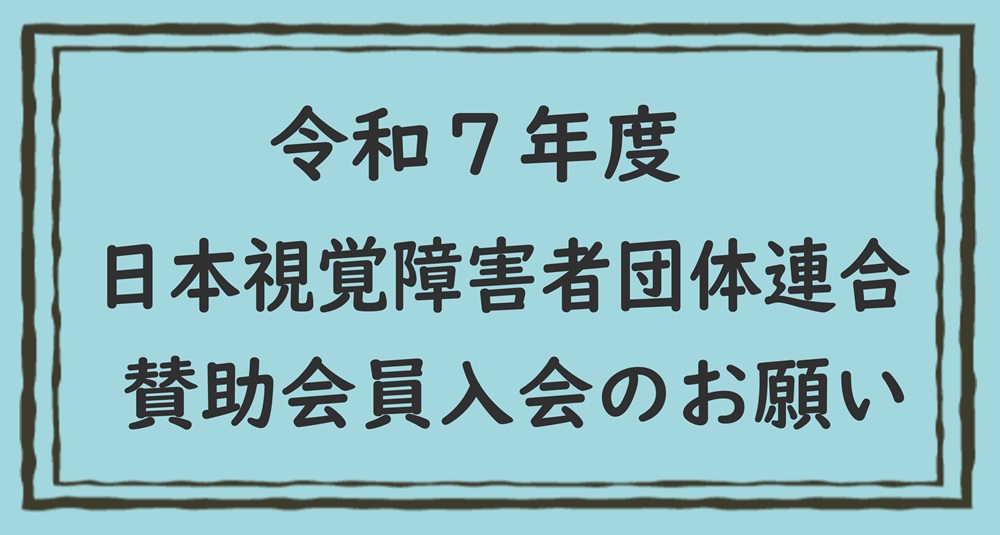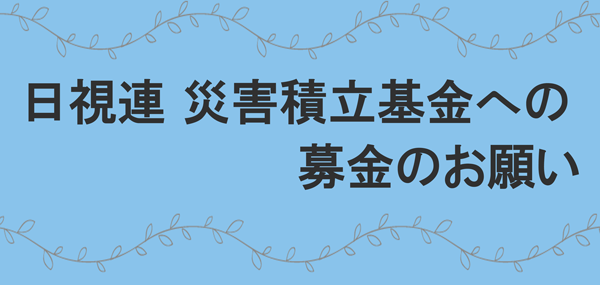厚労省・こども家庭庁の障害児・者に係る会議(2)
令和7年1月30日、社会保障審議会障害者部会(第145回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第10回)合同会議がベルサール飯田橋駅前においてオンライン参加も交えて開催され、日本視覚障害者団体連合からは大胡田誠将来ビジョン推進委員会委員長が構成員として、並びに竹下義樹会長の代理で吉泉豊晴情報部長が参考人として出席しました。
今回の議題は障害保健福祉施策の動向で、協議事項としては1.障害福祉分野における運営指導・監査の強化、2.障害福祉分野における手続負担の軽減、3.障害福祉サービス事業者等の経営情報の見える化の3項目。そのほか報告事項として4.新たな地域医療構想における精神医療の位置付け、5.「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会、6.就労選択支援、7.障害者虐待事例への対応状況調査結果等が取り上げられました。
運営指導・監査の強化は、株式会社恵の不適切な事業運営及び営利法人が運営する事業所数の急増を受けて行政による監査を強化するもの。手続負担の軽減は、手続きの標準化・デジタル化により事業者の負担を軽減するもの。経営情報の見える化は、安定した事業運営に支えられた良質なサービスを受けることができるかを利用者が判断できるよう財務書類等を公開するもの。
協議事項に関連して大胡田委員は、監査の強化は必要だが、事業者に過度な負担がかかって本来の業務に支障が出ることがないようにすべきであること、手続きに係る負担軽減は標準化・デジタル化だけでは実現できないので手続きそのものを簡素化すべきであること、及び電子媒体による手続きは視覚障害者も行えるものとすべきことを述べ、また、資料に「令和7年度中に障害福祉分野の運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方の例を作成する」とあるが、事業者の意見も踏まえながら作成した上で予め公表されるのかを質問しました。
これに対し事務局からは何らかの形で各種の意見を参考にして作成し公表したいとの回答がありました。吉泉参考人は、運営指導・監査の強化に関連して、監査が適確に行われるよう担当の人員を増やすべきこと、行政のチェックだけでは十分とはいえないので事業所の職員・利用者・その家族の通報を適切に取り扱い監査に生かすべきこと、監査の強化を周知することが不適切な運営の抑制効果を持つ可能性があるので周知徹底してもらいたいこと、また、経営情報の見える化については視覚障害者が把握しやすい形でもデータを公表してもらいたいことを述べました。
報告事項の「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会は、人口減少のスピードが地域差はありながら速まることを念頭に地域包括ケアの維持・必要な支援体制の整備を検討するものですが、大胡田委員は、検討会に障害者代表の委員が含まれていないことを指摘し、障害者団体へのヒアリングを行い意見を聞くべきであると述べました。
就労選択支援は、就労移行支援・就労継続支援・一般雇用を希望する障害者を支援するため就労能力等のアセスメントを行い、その結果を支援機関の間の連携に生かすものですが、吉泉参考人は、受け皿となる支援機関や就労の場が地域にあるとは限らないことを踏まえて、就労能力に着目するだけでなく地域の実情等を踏まえてアセスメントを行うべきであると述べました。これについては他の委員から、就労にかかわる障害者の意思の尊重を前提とすべきことなど様々な意見が出されました。